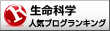黄色くて、小さく、はかない光が。
蛍です。D.C. のナショナルモール内にもちらちら、NIH 構内にもちらちら、そしてポトマックの家の周辺にも…。
かわいらしい光がはかない。
あまりにたくさん舞っているので、近づいてみますが、簡単に捕まえられます。たくさん飛んでいる、ホタル。
 |
| Fig.1 ホタルをつかまえてみた |
日本ではホタルといえば、ゲンジボタルとヘイケボタルの2種類ぐらいなのかな、水棲なはずで、最近は環境が良くなくて減っているのかな、アメリカは環境いいのかな…なんて漠然と思って、聞いてみたり調べてみたりしました。
結論から言うと、これらの疑問は全部正しくなかった…のです。
アメリカでみかけるホタルは陸棲なんですね。幼虫は木の陰で、カタツムリなどを餌にして生きているようです。
そして、実はホタルは陸棲がメジャーで、日本でみられる水棲の方が珍しいのだとか。日本国内では約40種類もいるそうです(源氏・平家だけではなかった…諸家ありということか)。
ホタルって、世界では 2000 種類もいるんですね。
ホタルの発光は、ルシフェラーゼ (luciferase, Luc) という酵素がルシフェリンという基質を ATP を用いて反応させて発光させるもので、冷光とも呼ばれる非常に効率よく熱損失のほとんどない形式によります。
このルシフェラーゼ、生物学の実験には非常によく使われており、ホタルルシフェラーゼ (firefly luciferase) は私も今使っています。ホタル以外の生物でもこのルシフェラーゼはあり、波長の違いか、うまく使えば様々な実験を組むことができます。
このルシフェラーゼの発光の謎に、X線結晶解析を用いて構造学的に迫った論文は、2006年に京大薬学部の中津先生、加藤先生が発表されています (Structural basis for the spectral difference in luciferase bioluminescence: Nature volume 440, pages 372–376 (16 March 2006、Spring8の報告、京大情報)。
個人的には、加藤先生に学部生時代にお世話になり、本当にすばらしい仕事をなされるんだなぁと思ったのはいまでも鮮明に覚えています。
ちらちらと舞う夏のホタル。美しいです。
アメリカに来られたら是非見てもらいたいものの一つになりました。