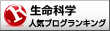|
| Fig.1 JP-AID のページより |
日経メディカル(2018/11/26) に「胃生検病理診断用のAI、診療現場での検証を開始」という記事が出ていました(会員でないと読めないかもしれません)。
日本病理学会秋季大会が行われていましたが、その中で2018年11月22日に記者会見が行われました。
病理学会がAMED事業として開発を行っていた、病理診断用のAI技術が実用化レベルに達し、福島・徳島県の診療現場で評価実験が始まるとのことです。
この事業は、AMEDに採択された「AI等の利活用を見据えた病理組織デジタル画像(P-WSI)の収集基盤整備と病理支援システム開発」という課題であり、事業名は「Japan Pathology Artificial Intelligence Diagnostics Project(JP-AID)」と言います。
今回、学会前にプレスリリースで予告がされていました。
▶ JP-AIDのページ - プレスリリース(平成30年11月9日)
実用化レベルに達した胃生検病理診断AIシステムが完成いたしましたので,ご報告の機会を設けました.広域ICT基板を用いた福島・徳島の地域病理診断ネットワークで,このAIエンジンを実装させる準備も重ねて進めています.
上記日経の記事によりますと、この課題で開発した胃癌診断用のAIは、996例の診断結果付き胃生検データをもとにディープラーニングをしたようです。
検証で、感度 93.3%、特異度 73.5%であり、病理医の診断とAIの判定の不一致率は16.2%であったとのこと。
このシステムを用いて、12月中に福島県では実験を開始し、今年度中に徳島県でも開始される予定とのこと。
プロジェクトの目標として現在、病理医とAIとの判定不一致率1割以下を目指しているそうです。
どんどん技術が進んでいくといいですね。楽しみです。
● 追加情報
読売新聞にも記事がでていました。
胃がん診断、AIが手助け…病理医の負担減