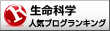マントル細胞リンパ腫に関する新しい論文が AJSP に出ていたので紹介いたします。
マントル細胞リンパ腫 (MCL)は、B細胞性リンパ腫で、indolent と aggressive の中間程度の悪性を示すことが知られており、形態学的には小~中程度の大きさの均質な細胞の単調または軽度に結節を形成するような増殖をしめし、免疫組織化学的には CD5(+)、CyclinD1(+)が典型的であるが、近年みつかった SOX-11(+)のことが多いのも特徴です。
臨床的には比較的白血化を引き起こしやすいことも知られています。
最近までの研究においては MCL のうち、SOX-11 を発現していることが予後度影響するかどうか、はっきりせず論点となっていました。
今回のこの論文では75冷のSOX-11陰性 MCL との比較によりその臨床病理学的特徴を解析しています。
それでは論文詳細です。
●
SOX11-negative Mantle Cell Lymphoma Clinicopathologic and Prognostic Features of 75 Patients
The American Journal of Surgical Pathology: February 12, 2019
Publish Ahead of Print
Xu J, Wang L, Li J, Saksena A, Wang SA, Shen J, Hu Z, Lin P, Tang G, Yin CC, Wang M, Medeiros LJ, Li S.
【概要】
SOX-11陰性MCL75例を検討した。
SOX-11陽性MCLと比較し、
より白血化が多かった(21% vs. 4%, P=0.0001)
より典型的な形態を呈した(83% vs. 65%, P=0.005)
よりCD23陽性の割合が高かった(39% vs. 22%, P=0.02)
よりCD200陽性の割合が高かった(60% vs. 9%, P=0.0001)
よりKi67陽性率が低かった(23% vs. 33%, P=0.04)
Overall Survival に有意な差はなかった(P=0.63)
一方、高いKi67陽性率と blastoid/pleomorphic
morphology は SOX-11陰性陽性にかかわらず
より短い Overall Survival と関連していた。
MCL の予後予測スコア(MIPI)でが高い場合、
SOX-11陰性の場合には有意に予後が悪く(P<0.05)、
陽性の場合には有意ではなかった(P=0.09)。
リンパ節病変ありまたは stage III/IV の場合には、
SOX-11陰性の場合には予後は有意に悪くはないが、
SOX-11陽性の場合には予後不良であった。
まとめると、SOX-11陰性MCL はより
白血化の頻度が高く、
典型的な形態で、
CD23・CD200の発現率が高く、
Ki67陽性率が低い。
SOX-11陰性MCL の予後因子は、形態、Ki67陽性率、
MIPIである。
【症例の選択】
テキサス大学アンダーソンがんセンターの
2004/1/1-2016/12/31 の MCL症例。
2016年 WHO classification に基づく分類。
IHCでCyclinD1(+)またはt(11;14)(q13;q32)
またはCCND1-IGH で診断を確定。
【結果の概要】
SOX-11陰性 MCL 75例、SOX-11陽性 MCL 146例。
【病理学的解析】
形態と免疫染色については Table 2 としてまとまっています。
【臨床的アウトカム】
略:(概要に示したものが代表)
【結論】
SOX-11陰性 MCL 75例、SOX-11陽性 MCL 146例の検討で、
SOX-11陰性 MCL はより白血化の頻度が高く、
典型的形態で、CD23・CD200発現率が高くKi67陽性率が低い。
SOX-11陰性 MCL の予後因子は、形態、Ki67陽性率、
MIPIであることがわかった。
MCL は indolent lymphoma と aggressive lymphoma の中間的な場合もおおい B細胞性リンパ腫であり、診断は比較的容易であることもあるものの、時に困難で SOX-11 は有用なマーカーとして報告されました。
リンパ腫の診断チャートは参考に ▶
峰式 リンパ腫の病理診断フローチャート
しかし、SOX-11 陰性 MCL もあるということがまず話題となり、SOX-11 の発現の有無でのふるまいについては議論が分かれているところでした。
今回紹介した論文では、SOX-11 陰性 MCL では白血化の頻度が高いことや、MIPI を用いて不良予後の予測ができそうであることなどが分かりました。
MCL についてはさらに詳細な生物学的な検討がなされそうに思います。
● 関連記事
▶
【血液病理】DLBCL の Hans の基準
▶
峰式 リンパ腫の病理診断フローチャート
▶
【書籍紹介】レベルアップのためのリンパ腫セミナー
▶
【書籍紹介】若手医師のためのリンパ腫セミナー
▶
【書籍紹介】見逃してはならない血液疾患 病理からみた44症例