その代わり快晴。
 |
| Fig.1 今朝の NIH 入口 |
寒いとやる気が下がりつつ、なんだかいろいろ委縮します。
今日はセミナーデー…なんだか疲れちゃうんですね。午前中でぐったりしました。
さて、ちょっとこのブログをつかって、今後、論文を読むという企画をやっていこうと思います。論文を読んで紹介している医療関係者ブログはたくさんありますし、医療関係のサイトなら論文サマライズなんかも人気コンテンツですよね。
独自性、というか、私の狙いは、一般の方でも論文になにがかいてあるかなーということがわかるように背景や論文の組み立て、方法その他をかみ砕きながら解説しつつ紹介するというスタンスのものです。医療従事者を対象とするものでも、ほら、数字がこうだからお前は間違っている、と論拠にしたり結果を利用するためのものでもなく。
どうやって論文を読むのかな、なにが書いてあるのかな、でやってみたい。
というわけで、どんな論文がよいかなーと考えています。
ま、論文読むのもいいけど、論文書けよ、というのは正論。
さて、FAES (▶ 紹介記事はこれです) で半期やってきた私の組織学講義は今日が最終講です。今日は試験と、次のステップへの道しるべです。
 |
| Fig.2 最終講資料 |
医学の知識というのは、経験的なものもたくさんありますし、整理して考えないと理解できないこともたくさんありますね。そして、学問というのは積み上げになっているので、基礎から丁寧にきっちりとやっていかないと、理解も利用も本来できません。
ここ数日、反ワクチンのような反知性的な方とのやりとりがちょっとあって感じたのは、積み上げた学習をしていないために何も理解できていない、それにも関わらず、都合の好さそうなデータや数字や、都合よく曲解したコメントをしてくれる人を容易に信じてなにもわからず、terminology さえ分からず、騒いでしまうというそういう悲しい実態があるということでした。
純粋に現象の記録やデータはあったとしても、学習の仕方や読み方考え方、そういったものはやはり積み上げないと何も身につかないんですね。
スポーツや武道であれば生兵法は怪我の元なんて、簡単にわかるのでしょうけど、学問もその最たるものだということがどうにもわからない方が多いようです。
私の生徒さんにはまず基礎を、基礎的な知識と、考え方を、そして枠組みのとらえ方と学習法を、さらに批判的に(自身にも学習対象にも)いることの大切さなどもお話しています。それこそが学問的な謙虚さですからね。
と、ま、そんなことはどうでもよくて、今日は試験をして講義をしないといけませんので、準備してのんびりしております。
夜は用事があるので、あまり寒くならないといいなぁ。

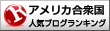
0 件のコメント:
コメントを投稿